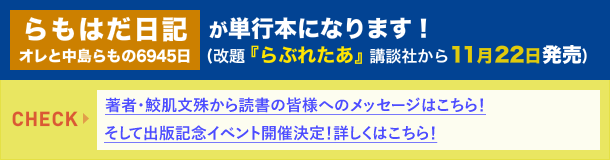1985年も終わろうとしていた頃。
中島らもは書き下ろしの小説を執筆中であった。
「キミ、昨日の晩、ホテルの一階の植え込みの木を引き抜いて部屋まで持って入ったやろ」
いつものようにオカマのヒコちゃんのバー「DO」で飲んでいる時に、らもさんに言われた。昨夜の記憶がフラッシュバック。
らもさんから「いま小説を頼まれて執筆中で大変」って話を聞きながら一緒に梅田の居酒屋で飲んだ。終電がなくなって帰れないので、そのままらもさんが缶詰になって泊まっているホテルまでついていって、部屋で一泊。
その時、何故かホテルの植え込みを見て「なんやこの木は。よし!全部引っこ抜いてやる」と酔った頭で思い、よいしょよいしょと一本、太めの木を引っこ抜いて部屋まで持って入ったのを思い出した。
「キミが朝方に起きて帰って。オレはず~~~っと部屋で原稿を書いてた。やっと一段落ついてチェックアウトした時にフロントで言われたんや。
『お客様、植え込みの木をお部屋にお持ち込みになるのはご遠慮願います』って。
クックックッ」
中島らも最初の単行本となる「頭の中がカユいんだ」はその時に書かれていたようだ。当時のらもさんのラリラリの日々を綴ったノンノンフィクションと銘打った私小説。
ロック界ではよく「ファーストアルバムには、そのアーティストの全ての要素が全部詰まっている」と言われるが、この作品もそう。
小説家、中島らものリリカルな面がストレートに吐露されていて、その後の物書きとしてのエッセンスがギューギューに詰まっている傑作。
読むと当時のことが思い出されて切なくなる。
本と言えば。
「頭の中がカユいんだ」が出版された後に、講談社から出た「ナニワのアホぢから」。
このムック本の執筆依頼をされたのも「DO」で飲んでいる時だった。
「今度な、講談社から企画モンの単行本を出すんや」
「あ、そうなんですか」
「キミ、マンガ得意やろ」
「ハイ。昔、漫画家になりたくて、中3の時に少年チャンピオンの漫画賞に応募して第3次審査までいったのが自慢です!」
「その本に載せる4コママンガを8本、来週までに描いてくれへんか」
「いきなりの発注ですね。ちょっと待ってくださいよ」
思いついたアイデアをメモってあるネタ帳をめくって数えたら、ちょうど8本分のアイデアがあった。
「描けますけど」
「本にキミのマンガも載せたい。ガンジーや、ひさうちみちおさんにも声かけてるねん。印税入ったら、みんなで宴会しよう」
しかし。
この単行本、間に入った東京の編集プロダクションがアホアホで、らもさんが「こうして欲しい」と言った約束を全面的に反故、出来上がったのは「関西人撲滅協会」と書かれた謎の団体名名義のよくワカラン本だった。
聞けば、初版八千部の約束が勝手に四千部に減らされたという。
ギャラもスズメの涙。
この時、「みんなで印税を山分けや」と執筆者全員に言っていたのに果たせなかった約束を、らもさんは長い間、負い目に感じていたようだ。
それから6年後、この「ナニワのアホぢから」が文庫化された。
ベストセラーを連発、超のつく売れっ子作家になっていた中島らも。過去の汚点と呼べるこんな本まで勢いで文庫化の運びとなったようだ。聞けば初版数十万部というべらぼうな数である。
中島らも事務所のマネージャーに就任していたふっこさんから連絡があった。
「中島が、あの時はすまなかったと申しております。今回の印税で勘弁してくださいとのことです」
ハッキリ言って、そんな昔の本のことをすっかり忘れていた自分。オレがやったことと言えばちょちょいっと4コママンガを描いて載っけただけである。
なのに。
銀行にドンッ!と振り込まれた額を持て飛び上がった。
60万円!?
額の大きさにぷるぷると震えたのを覚えている。
駆け出しの放送作家として上京したてで貧乏していた時期だったので本当にありがたかった。
こんな風にらもさんはお金に関して、凄く義理固い。
仲間にちゃんとしたギャラという対価を払って仕事をするのにこだわっていた。
リリパット・アーミーにしてもそうだった。
演劇なんて食えなくて当たり前。なんだったらチケットノルマを押しつけられて役者の持ち出しになるのが常識だった小劇団の世界で、初めっからキチンとギャラを払っていた。
オレもお世話になりっぱなし。
しかも知り合ってから数年、らもさんは飲み代を全部出してくれていたのである。
あまりにも悪いので恐縮して「今回はオレに出させてください」と行ったところ、こう諭されたのを覚えている。
「あのな、キミ、自分が金を稼げる年になった時に、今度は下の奴に奢ってやれ。オレも上の人にそうしてもらってきた。若い奴は金がないやろ?金はある奴が出したらええねん」
らもさんが師と仰いでいた先輩広告マンで電通大阪支社所属の伝説のコピーライター、藤島克彦さんから教えられた言葉だそうである。
当時、一世を風靡したキンチョールの「トンデレラ・シンデレラ」をはじめヒット作を連発していた藤島さん。面識はなかったが、
らもさんからよく話は聞いていた。
元々、コピーライターになるために通っていた「宣伝会議」の講座で、講師と生徒として出会い、気に入られて1年間、師事していたらしい。
毎日のように飲みに連れて行ってもらっていたという。
なんだ。まるで、らもさんとオレのようじゃないか。
その方、不運にもあの日航機墜落事故で亡くなられた。
「鮫肌、ついて来い!」
その先輩の行きつけのバーを一晩で全部回って、先輩名義でキープしてあったボトルを次々に空けていった。らも流の供養だったんだと思う。
らもさんのそんなダンディズムも、一緒に飲みまくっているうちに教えてもらった。
今も私の後輩に当たる若者たちには、らもさんの教えを守って全部奢るようにしている。
雲雀丘花屋敷の自宅のリビングで、日本酒を飲みながら、「稼いでも稼いでも貯金なんて全然あらへんよ、クックックッ」と笑っていたらもさんを思い出す。
(つづく)