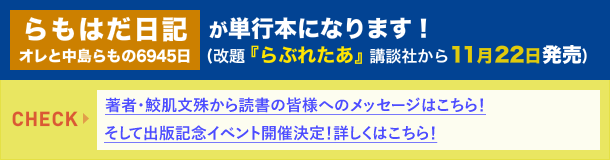1985年10月から翌年の1月まで。
わずか12回、ワンクールもたずに打ち切りになった伝説の番組「なげやり倶楽部」。
この番組、トークやライブのゲストも尖っていたが、それ以上に尖っていたのがコントコーナー。今考えても超豪華。
竹中直人、いとうせいこう、中村ゆうじ(現・中村有志)、シティボーイズというラジカル・ガジベリビンバ・システムの面々が、中島らも書き下ろしの新作コントを毎週毎週演じていたのだ。
コント収録の合間に、よく大竹まことさんが漏らしていた。
「最近、東京で仕事をしながら、よくメンバー同士で、早く大阪行って、らもさんの番組でコントやりてえ、演出のツジさんと仕事してえ! って言い合ってるんですよ」
東京の深夜番組でもここまで自由にやらせれくれる場はなかったのであろう。
スタッフの一人として、現場でその話を聞きながらとても誇らしかった記憶がある。
通常、この手のコント番組は、数人の放送作家を抱えている。それぞれの作家に自分の面白いと思うコント台本を書かせ、総合演出まで提出させる。時には数十本にもなるその台本を総合演出が「採用。不採用。とりあえずキープ」って感じで選別。採用になったものから収録されていくシステムが多い。
放送作家も、出演者がわかっている場合は「このコントは竹中直人で」という風に指定して台本を書くこともある。いわゆる「あて書き」ってヤツだ。
しかし、コントを撮るには手間とお金がかかる。例えば「遠山の金さん」をパロディにしたコントを撮ろうと思ったら、スタジオに実際にお白洲を建て込まなければならないのだ。よってリーマン・ショック以降、制作費が激減したテレビの現場ではコント番組は敬遠されている。
今考えると、まだバブルも来ていない「なげやり倶楽部」をやっていた時代のテレビ局には、ちゃんとコントを撮るだけのお金と余裕があったんだなと思う。オレはらもさんのおかげで、とても幸せな時期のテレビ業界でデビューを果たしていたのだ。本人に「放送作家をやっている」って職業としての自覚はゼロであったが。
「なげやり倶楽部」においてメインライターとしてコントを書いていたのは、らもさん。でも毎週毎週撮っていくのでどうしても数が足りなくなる。
そこで番組に参加していたブレーンにもお鉢が回ってきた。
「キミも、書き」
らもさんにそう言われて、今考えると恐れ多いのだが、そこは若さゆえの厚顔無恥。オレもこんな超一流のコメディアンの方々に対してコントを書いていた。
例えばこんなコント。
○乳母車を押す女(大竹まこと)
乳母車の中には、扇風機。
カバーを外した扇風機の羽が唸りをあげてブンブン回っている。
○そこに通りがかる近所の主婦2人(きたろう、斉木しげる)
テンパった様子の乳母車を押す女が、通りかかった主婦とすれ違いざまに叫ぶ。
「子供ッ!」
それを受けた2人。
完全に可哀想な人を見る目で。
「そう、子供なの」
「可愛いわね~」
すると、女が返す。
「指ッ!」
「あら、指?こうすればいいのかしら?」
女に言われるまま、ブンブン回る扇風機の羽を指で触ろうとする主婦。
バチッ!
扇風機の羽に指が当たって。
「痛いッ!噛んだ。この子、噛んだわ!」
それを見た乳母車を押す女が、虚空を見つめて絶叫する。
「子供ーーーーー!ッ!」
実際にこんなワケのわからないコントを撮って地上波でオンエアしていたのだ。
何が面白いのか自分でもさっぱりわからない。とにかく気が狂ったキャラクターを出していれば過激なんだと勘違い。完全にシュールを履き違えていてお恥ずかしい限り。
このコントを撮った時の事を今でも覚えている。
スタジオにやってきたシティボーイズの3人。ツジさんから、オレの書いたコント台本を見せられて読む。
リーダーの大竹まことさんが一読してボソッとひと言漏らす。
「このコント、オチがないよね」
斉木しげるさんも同調する。
「うん、オチがないね」
らもさんの書くオチがはっきりした演じやすいプロのコントと比べて、シュールを履き違えたオチの無いオレのコントに、明らかに「やりたくねえ」オーラを出す2人。
「このコント、誰が書いたの?」
大竹まことさんが聞く。
「ここにいる鮫肌が書きました」
ツジさんが答える。
「ふ~ん」
大竹まことさんが冷たい目でオレを見る。
コントの収録現場には毎回立ち会っていた。らもさんの書いたコントの収録では無責任にゲラゲラ笑っていれば良かったが、自分の書いたコントでは違う。コントって、こんな風に書いた作家が矢面に立たされることもあるのか。初めての経験。背中に冷や汗がたらり。このまま「やっぱりこんなオチの無いコント台本じゃやれない」って演者に言われればアウトだ。
しかし、すでにスタジオにはこのコントを撮るために乳母車などの小道具も衣装も用意されてしまっていた。
「ま、とりあえずやりますか!」
きたろうさんが明るく言い放つ。
渋々立ち上がる大竹さんと斉木さん。
その救いの言葉で、なんとかコントの収録はスタート。
しかし、本番が終わってカットのかかった直後、大竹まことさんが汗びっしょりになりながらこう言ったのが忘れられない。
「心の中で、『オチがない、オチがない、早くツジさんからカットの声かかってくれ~』って叫びながらやってたんだよね」
申し訳ないことをした。
同じく現場に立ち会っていたらもさんにもこう言われた。
「キミの書くコントは、キチガイが一人出てきて暴れるってワンパターンしかないな。これから作家としてやっていくなら、もっと笑いのパターンを持っとかなアカンで」
さすが中島らも。オレのコント作家としての弱点を一発で言い当てやがった。
とてもヘコんだ記憶がある。
しかし、コント職人・中島らもの書くベタなコントと、オレみたいな放送コードなんか無視した学生作家の書くダメダメコントが玉石混交となって番組に勢いを与えていたのは間違いない。

らもはだ日記
- 第一回 10/19 UP
- 第二回 10/26 UP
- 第三回 11/02 UP
- 第四回 11/09 UP
- 第五回 11/16 UP
- 第六回 11/23 UP
- 第七回 11/30 UP
- 第八回 12/07 UP
- 第九回 12/14 UP
- 第十回 12/21 UP
- 第十一回 12/28 UP
- 第十二回 1/4 UP
- 第十三回 1/11 UP
- 第十四回 1/18 UP
- 第十五回 1/25 UP
- 第十六回 2/1 UP
- 第十七回 2/8 UP
- 第十八回 2/15 UP
- 第十九回 2/22 UP
- 第二十回 2/29 UP
- 第二十一回 3/7 UP
- 第二十二回 3/14 UP
- 第二十三回 3/21 UP
- 第二十四回 3/28 UP
- 第二十五回 4/4 UP
- 第二十六回 4/11 UP
- 第二十七回 4/18 UP
- 第二十八回 4/25 UP
- 第二十九回 5/2 UP
- 第三十回 5/9 UP
- 第三十一回 5/17 UP
- 第三十二回 5/23 UP
- 最終回5/30 UP