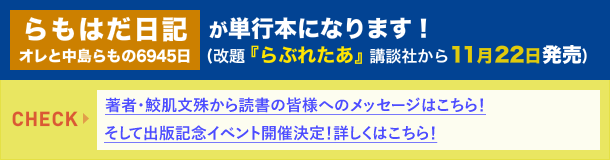1986年4月。
らもさんが、劇団「笑殺軍団リリパット・アーミー」を立ち上げた。「なげやり倶楽部」でテレビの中の表現の不自由さにほとほと愛想がつきた中島らもが「舞台やったら何のタブーもないやろ」とおっ始めたのだ。
まず最初の顔合わせ。
らもさんの知りあいの広告代理店の会議室を借りて。
メンバーは、らもさんが「顔が面白い」って理由のみで選んだ人たち。
編集者のガンジー石原、漫画家のひさうちみちお。
ラジオ「月光通信」のスタッフだったキモトに至っては、「元ヤンキー」という肩書きだけで呼ばれていた。
プロの役者側には、「なげやり倶楽部」にも出演していたコメディエンヌ、女優の牧野エミさん。劇団満開座から、仁王門大五郎さん、清瀬順子さん。
「よろしくお願いします」
そして、もう一人。ちっちゃくてとても可愛い女性に挨拶された。
中島らもの周りには何故かいつもちっちゃくてコケティッシュな魅力を持つ女性がいてあれこれと身の回りの世話を焼く。
「わかぎゑふです」
らもさんと古くからの友人というその女性。彼女が今回、らもさんと劇団を一緒に立ち上げた人らしい。
東京で芝居の勉強をしていて大阪に帰ってきたところだという。
らもさんが「ふっこ」と呼んでいたので、みんな「ふっこさん」と呼ぶようになった。
初対面の時、敬語であんなに礼儀正しかったのに、まさかふっこさんにこの後、一生分叱られることになろうとは全く思っていなかった。
らもさんが旗揚げ公演用に書き上げた台本「X線の午後」。
これまで書きためたコントをこれでもかと叩き込んだ、お客さんに「とにかく笑って帰ってください」というハードコアな内容。ストーリーもへったくれもない、劇団名「笑殺軍団」に違わぬコント100連発な構成である。
絶対にテレビじゃ出来ない、けどとにかく面白い。そんな笑いの速射砲のような芝居になるはずだった。
だがそれもちゃんとした役者がやればの話。
らもさんはあまりにも演劇をナメすぎていたのだ。
劇団員の半分以上が、小学校の学芸会でも「木」の役しかやらせてもらえなかったような演劇に関してズブの素人ばかり。
「タバコとペン以上に重いもんは持ったことがおまへんなぁ」と嘯く超文化系のド素人たちに芝居をやらせる。これはいわば「現地から連れてきたジンバブエの若者に、いきなり紅白歌合戦の総合司会をやらせる」くらい難しいことであった。
そんな困難にひとり立ち向かったジャンヌダルク、わかぎゑふ。
中島らもの周りには、いつもちっちゃくてコケティッシュな女性がいてあれこれ世話を焼くと書いたが、もうひとつ書き忘れていた。みんな、小さいのに男勝りで気が強いのである。
らもさんの嫁のミーさんもそうだが、ふっこさんはその中でも最強。
借りていた稽古場に、ふっこさんの怒声が響く。
「キッチュ!」
「ガンジー!」
「おっちゃん!」(らもさんのことを、ふっこさんはこう呼んでいた)
いい年をしたオトナたちが、ちっちゃいふっこさんに怒鳴られまくり。
ひさうちみちおさんが稽古場の隅っこで独り言。
「そんなにやいのやいの怒らんでも、ねえ~」
間髪をいれずにふっこさんが返す。
「怒らなでけへんから怒るんや!」
「ひえ~、くわばらくわばら」
一回りは年の違うひさうちさんも形無し。
「ひさうちさんがガロに描いてた耽美派マンガのファンで、女子高生の頃憧れてたのに。会ってみたら何もでけへんただのおっさんやった。ほんまに会わんかったら良かったわ!」
ふっこさん、よくそう言っていたなあ。
それでも最初は、ひさうちさんを初め、ふっこさんも年上のメンバー達に気を使っていたのである。
名前も「ガンジーさん」と、さん付けで呼んでいた。しかし、「こいつらに気を使う必要がない」と気づいたようだ。すぐに「ガンジー」と呼び捨てになった。
でも、呼び捨てにされても仕方ない。
だってこのメンバー、とにかく演劇的な動きが全く出来なかったからだ。
中でも、ふっこさんの前になると「また怒られるかも」とド緊張する「ふっこ恐怖症」に陥ったのがガンジーさん。
例えば、ふっこさんがコントの演出で、ガンジーさんにこう言うとする。
「歩いてみて」
するとガンジーさん、緊張して右手と右足が同時に出てしまうのだ。
どれだけ怖がってるねん。
「そこから始めなアカンのんかい!」
ふっこさんが思わず汚い関西弁でブチ切れてしまうのも致し方なかった。
「す、す、すいまへ~ん。ご、ご、ご勘弁を~」
ガンジーさんの、世にも情けなく弱々しいお詫びの言葉が、今日も稽古場に響くのであった。
ふっこさんの怒りの矛先はガンジーさんだけでは無い。座長の中島らもにも容赦無かった。
ある時、稽古場に行く前、集合時間まで30分ほど余裕があった。
「鮫肌、ちょっと行こか」
誘われて2人で正宗屋へ。
今考えると、座長の中島らも自ら一杯ひっかけて来るなんてありえないことであるが。
赤ら顔で稽古場に現れたらもさんを見たふっこさんが呆れ顔で聞く。
「おっちゃん、もしかして……飲んでる?」
「……うん」
「うん」の「ん」まで言い終わらないうちに、ふっこさんの張り手が、中島らもの左頬に跳んだ。
鉄拳制裁!
かけていたサングラスがポ~ンと宙を舞う。
サングラスってあんなに遠くまで飛ぶんだと惚れ惚れするくらい切れ味抜群の張り手。
つくづくふっこさんの張り手は芸術的だったなあ。
稽古場の片隅まで飛んでいったサングラスをすごすごと取りに行く座長・中島らも。
これ以後、リリパット・アーミーの稽古場では、そんな情けない中島らもが「よくある光景」となる。
さすがにそれかららもさんも、ふっこさんを恐れて一杯ひっかけて来るなんてしなくなった。
しかし、いくらふっこさんに怒られても劇団に関してお仕事モードの役者陣と比べて、素人のオレたちはどこかお遊びモード。
稽古が終わった後の飲み会だけを目的に集まっていたようなものであった。
公演が近づくにつれて、ふっこさんのイライラもピークに達しようとしていた。
「文殊ッ!ええかげんにしいや!!」
もう50歳にもなろうかと言うのに、未だにふっこさんに叱り飛ばされる夢を見て全身寝汗グッチョリで目が覚める。
ハッ! と飛び起きて周りを見回せば、そこは自分の家のベッドの上。
「夢やったんや」
完全にトラウマになっている。たぶんこの頃、一生分、叱られたと思う。
自分が「何か書くこと」以外に何も出来ない唐変木なことを、ふっこさんに思い知らされたリリパット・アーミーの稽古の日々。
でも、こんなに楽しい日々はなかった。
リリパット・アーミーのあの「ゆるさ」と「楽しさ」は独特で、何ものにも例えようがない。ひたすら、アホな人たちと芝居の稽古という名の「遊び」にいそしんでいた毎日。
なんだったんだろう、あの頃のリリパット・アーミーって?
「文殊!そのカゲで私がどんだけ苦労したと思ってるねん!」
呑気にこんなこと書いていると、ふっこさんにまたどやされそうであるが。

らもはだ日記
- 第一回 10/19 UP
- 第二回 10/26 UP
- 第三回 11/02 UP
- 第四回 11/09 UP
- 第五回 11/16 UP
- 第六回 11/23 UP
- 第七回 11/30 UP
- 第八回 12/07 UP
- 第九回 12/14 UP
- 第十回 12/21 UP
- 第十一回 12/28 UP
- 第十二回 1/4 UP
- 第十三回 1/11 UP
- 第十四回 1/18 UP
- 第十五回 1/25 UP
- 第十六回 2/1 UP
- 第十七回 2/8 UP
- 第十八回 2/15 UP
- 第十九回 2/22 UP
- 第二十回 2/29 UP
- 第二十一回 3/7 UP
- 第二十二回 3/14 UP
- 第二十三回 3/21 UP
- 第二十四回 3/28 UP
- 第二十五回 4/4 UP
- 第二十六回 4/11 UP
- 第二十七回 4/18 UP
- 第二十八回 4/25 UP
- 第二十九回 5/2 UP
- 第三十回 5/9 UP
- 第三十一回 5/17 UP
- 第三十二回 5/23 UP
- 最終回5/30 UP