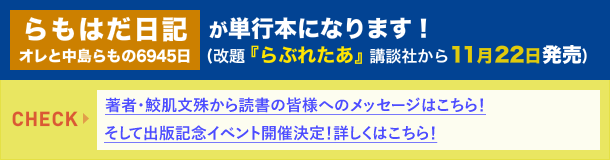2004年8月22日。
今日も前夜の深酒でド二日酔いのまま、新幹線に乗って大阪へ。梅田で阪急電車に乗り換えて雲雀丘花屋敷駅に着いた。
ほぼ16年ぶり。
お別れを言いにらもさんの家にやって来た。
駅から、歩く。
もう何百回、この駅からの道を歩いたことだろう。20代前半、毎日のようにベロベロに酔っ払って押しかけては泊まっていたらもさんの自宅までの道順が歩いているうちにどんどんと甦る。記憶通りの風景が目の前に広がっていく。
らもさんに「顔を覚えられて、もう売ってくれへんから」と、ブロンを買ってきてくれと頼まれた駅前の薬局もまだあった。駅からちょっと歩いたところの踏切もそのままだ。踏切を渡ると、今度は閑静な住宅街へと入っていく。
ここの家も、ここの家もそのまんま。思い出す、思い出す。景色が全く変わっていないため、なんだかタイムスリップしたような感覚に陥る。
キッチュさんが「自宅に出向いて、らもさんにさよならを言いたい」と電話したら「その日は用事で外出てるから、ドア開いてるんで勝手に中入ってやっといて!」と、奥さんの中島美代子さん、通称ミーさんに言われて、ホントに一人で家に上がり込んでお別れをした話を聞いていた。
ミーさん、変わってないなあ。
中島らものグッチャグチャの人生、普通のパートナーだったら気が狂ってしまっていただろう。
オレが行った日は運良く家にいたミーさん。
「よく来たね、鮫肌!」
笑顔で出迎えてくれた。
うさぎに蛇に、熱帯魚に。犬をはじめ昔もいっぱい動物を飼っていたが、その数も種類もさらに増えていた。
ミーさんに挨拶。
「らもさんに会いに来ました」
らもさんに教えてもらったウイスキー、IWハーパーのボトルを持参していた。自分の金で飲めるようになってからウイスキーと言えばハーパー一本槍。
ミーさんに案内されて、リビングの隣の部屋へ。
らもさんの使っていた二段ベッドがそのまま残されている。
布団の上に無造作に置かれた骨箱。みんなの持ってきた酒瓶に囲まれてすっかり小さな骨になった中島らもがゆっくりと眠っていた。
骨箱の横にハーパーのボトルを寝かせて、天国のらもさんに捧げる。
らもさんにお別れを言いにこの家に来たはずなのに。
机の上には、頭をカチ割った日に家を出た時そのまんま書きかけの原稿が置いてあった。
けして続きが書かれることのないその原稿。らもさんの手書きの几帳面な文字が並んでいる。
次の小説用だろうか。
詳細なプロットがびっしりと書きこまれたメモ用紙もあった。
「小説を書く時は、書きたいことをひとつひとつメモにして並べる。それが300枚くらい溜まったら1本出来るんや」
そんなこと言ってたな、らもさん。
起き抜けにいつもコーヒーとブロンを飲んでいたリビングのテーブルの周りには、次に読むための本の山が積んである。
神経痛そうに灰皿に一本一本円形に並べられた吸い殻もそのまんま残っていた。
中島らもの生きている「気配」そのままがこの家には真空パックされている。
「クックツクツクツ………」
今にもらもさんの特徴あるアノ笑い声が聞こえてきそうだ。
こんな死に方ってあるか?
最後の最後までキメやがって。
ええかっこしいにもほどがあるよ、らもさん。「突然死ぬなんてロックっぽいやろ?」って笑っているのか。
ミーさんが言う。
「死んだ直後、らもがここに帰ってきたみたいで犬が「らもがいる、いる」って鳴くの」
オレも感じていた。
この部屋には、まだ中島らもが確かに居る。
まだ当人も死んだ気がしてないんじゃないだろうか。
だからオレも、祈りもしないし、「さよなら」も言わなかった。
それから、ここに来ていなかった16年の時間を埋めるように、ミーさんとらもさんの話を延々とした。
リビングのいつもらもさんが座っていたイスに人の「気配」を感じながら。
2人の話を聞きに来ていたのかもしれない。
気がつくともう3時間半も経っていた。
ミーさんが言う。
「死んだ時の写真、見る?らも、ジュリーみたいに綺麗でかっこいいんだよ!」
「ねえ、ねえ、鮫肌。らもの骨、一個持って帰る? 山内は一個持っていったけど」
せっかくだけど、どちらも断った。らもさんの死を認めたくなかった。
だって、らもさんはまだそこに居るじゃないか。
死んでなんか、ないよ。
らもさんの家を出て、またふらふらと駅まで戻った。
そのまま帰りの新幹線の中でも飲みまくって泥酔。
東京に戻って、歌舞伎町に友人を呼び出してさらに飲みまくり。
思えば、知り合った頃は全然酒が飲めなかった。飲めば食べた以上に吐くオレに「クラインの壺」ってアダ名をつけた、らもさん。
酒に強くなって、もう何年も吐いていなかったが、その日はかつて中島らもから「クラインの壺」と呼ばれていた頃のようにしこたま飲んで吐いた。
吐いて吐いて吐きまくった。
(つづく)