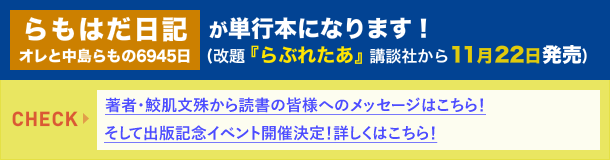1986年6月23日。
笑殺軍団リリパットアーミー旗揚げ公演の日。
演劇的技術ゼロ。ほぼノリと勢いだけで迎えた本番初日。
開演1時間前。なにぶんにもド素人ゆえ自分で役者の基本中の基本、メイクをすることさえままならない我々が、まるでエサをもらおうと一生懸命首を伸ばすスズメの雛のように、ふっこさんの前に「メイク早よしてんかア」と列をなして並んでいた。
他の劇団では絶対にありえないそんな情けない風景が、初期のリリパット・アーミーでは本番前の風物詩となる。
しかし、そんなトホホな我々を見に、劇場となった扇町ミュージアムスクエアには山のようなお客さんが押し寄せていた。
朝日新聞連載の「明るい悩みの相談室」の人気や「なげやり倶楽部」での司会など中島らもが関西でブレイク中だったこともある。
「あの中島らもが劇団を始めるんやて。いっぺん見といたろ」
関西中の自称「トンガリキッズ」たちが押し寄せて来たのだ。
客席の真ん中に柱が建つという特殊な形状の劇場だった扇町ミュージアムスクエア。よって、その柱の後ろは影になって舞台が見えないため、通常、お客さんは入れない。
「舞台が見えなくていいんです!声だけでも聞かせてください!」
満席で入場を断ったお客さんにそう訴えられて、そこは関西人。判断は早かった。
ふっこさんが決断する。
「もうええ!全部入れてしまえ」
ついに、柱の影も開放。
消防法なんて完全無視で詰めるだけ詰め込んで文字通りすし詰め状態の客席。
「もう入らない」
そこに、手伝いのスタッフで来ていた中島らも夫人、ミーさんが。
「私に任せて!」
舞台に出て行った。ミーさんは、元小学校の司書。この手の「集団行動」の指示には慣れている。
「中島らもの嫁です!」
客席から拍手。
「入りきれないお客さんがまだ外に大勢います。一人でもたくさんの人に、らものお芝居を見せてあげたい。あと数センチずつ前に詰めてくれませんか」
さすが、元司書。
言葉に説得力。もう限界のはずなのに思わず言われた通りに従ってしまうお客さんたち。
ギッチギチのギチ。
ギューギュー詰め。
なのに、まだ客が入ってしまうミラクル!
はっきり言って、開演前から、こんな熱気帯びまくりな見たことがない狂躁状態。
あとは、何をやってもウケる。
箸が転んでもおかしいって言葉があるが、中島らもが出て行っただけでドカン。
何か喋る度にドカン。
若者だらけの客席は笑いの入れ食い。
父親役のらもさんに、息子のパンクス役のオレ。舞台に演劇のド素人2人しか出ていないオープニングシーンから、ドカン。劇場が揺れるぐらいの笑いが起きた。
演劇のド素人集団を率いてここまでこぎつけて、ふっこさんもさぞ苦労の甲斐があったことだろう。
舞台の袖で、満足気な表情を浮かべているかと思いきや。実はふっこさん、後で聞いたのだが本番中もそれどころでは無かったらしい。
舞台裏では、彼女が判断して即座に対応しなければならない大きなトラブルが起きていたのである。
後援スポンサーは、関西では知らない人がいない練り物メーカー、カネテツデリカフーズ。社長が、らもさんと同級生だった縁でスポンサーに。
初日、入場時に客に配っていたカネテツ自慢のちくわのサンプル商品。2日目、あまりの観客の多さに大混乱だった受付が配り忘れた。痛恨のミス。
「どうしましょ、ふっこさん?」
オロオロするばかりの制作スタッフ。
「ええい!いっそ舞台から放り投げてしまえ!」
ふっこさんが叫んだ。
これがリリパット・アーミー名物となる「ちくわの狂い投げ」をやるようになったきっかけ。
以後、カーテンコール時にはこれが定番となる。
我々の投げるちくわを求めて総立ちになり、まるでロックコンサートのようなノリの客席。
なんやこれは。
アホや。
超満員の客の上を飛び交い、宙に舞うちくわ数百本を舞台から眺めながらオレは、目の前に広がるこの世のものとは思えないお祭り騒ぎを心の底から楽しんでいた。
こんな楽しい楽しい日々が永遠に続いたらええのになあ。
◆
「らもさんが、アル中で入院しました」
ふっこさんから、中島らも最初の入院を知らせる電話がかかってきたのは、リリパットアーミー旗揚げから1年半経った1987年の暮れのことだった。
(つづく)